「もう二度と口にするな」
放たれた言葉に、愛などなかった。どうして、と言いたげなの虚ろな瞳からは、大粒の涙が頬を伝いこぼれ落ちている。止めなく流れる涙をどうにかせき止めようと、ぐっと下唇を噛み締めてこらえる彼女の姿を見ても、ジャックの心が痛むことは無かった。愛だの恋だの友情だの、頬を撫でる春風のような感情も全て、このごみ溜めに捨てると決めたのだ。その覚悟が揺らがぬよう、冷徹に、棘を身体中に張り巡らせて、鋭く立ち振る舞う。泣きたいのなら、ずっと泣いていればいいのだ。
「さよならだ」
塊のように動かなくなったを尻目に、踵を返す。
後悔はない。
己の選んだ道が、間違いであるはずがないのだ。
「二度と、オレの名を口にするな」
不動遊星から奪ったDホイールに跨って、念を押すように彼は言う。咎めるというより、願いに近い口調であった。この瓦礫に埋もれた世界への、最後の願い。もうオレを苦しめないでくれ。自由にしてくれ。お願いだ。
波の音にかき消されそうなほどか細いの声が、ジャックに静止を求めた。痛ましげな視線がジャックの背中に突き刺さる。それでもジャックは、自身の行動を止めることはない。傍に転がっていたヘルメットを被り、エンジンを起動させる。彼の固い決断はもはや誰にも止められるものではないのだ。
何もかもが零れ落ちていった。悲しみも愛おしさも希望も絶望も全て。ハンドルを握る指先がチリチリと痛む。口内が干上がった砂漠のようにカラカラと乾いている。身に起きている事象全てが喪失感を加速させていく。全てが混ざり合い、この地に溶けていく。
世界で一番愛おしい女が、自分のためだけに泣いている。ただそれだけを、待ち続けた。
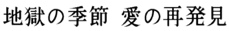
例えばの話だ。ジャック・アトラスが今この場で、に、カスタードクリームに蜂蜜をかけたような甘ったるい愛のセリフを囁いてみるとしよう。「お前が必要なんだ」、「一生お前だけを愛してみせる」なんてのもいいかもしれない。
するとどうだ。そんなジャックらしからぬ台詞を囁かれたはというと、眉尻を下げ、困り果てたような顔つきになった後、苦笑するだろう。返ってくる言葉は知れている。
「冗談でしょ?」だ。
それも、軽々とした口調の。
の遣り口など、想像は容易い。誤魔化すにも、惚けるにも、有耶無耶にするにも持ってこいの返答であると分かった上で言っているのだ(少なくともジャックはそう考えている)。
人を疑うなんておよしなさい、とマーサなら叱り倒すだろう。とはいえ、ジャックがこういった疑心暗鬼に似た複雑な心境を抱く原因はきちんと存在している。それがどのくらい前の出来事であったか、詳細に関してはジャック自身もうろ覚えであるのだが、おおまかに言えばジャックがマーサの元で世話になっていたころだ。
あの頃はよく夕暮れ時に、マーサの目を盗んで、と二人で海辺から見えるシティのネオンを見に行った。きらびやかなネオンに憧れを抱いていた幼きジャックは、とある日に、感情の高ぶりの勢いが余って「オレがキングになれたら結婚してくれ」とに一世一代の告白をしたのだ。実に青臭く、思い返すだけで穴があったら入りたくなる衝動に駆られる黒歴史そのもだ。
だが、その時の彼はまだ10にも満たない子供であったものの、当時のに対して、抱き、芽生えていた感情は、嘘偽りの無い、憧れでも愛情への飢えでもなく、真実であったことに間違いは無かった。
しかし、その際にから返ってきた返答は、
「冗談でしょ?」
……だった。
今でもジャックは、彼女が何をどう冗談として受け取ってしまったのかを理解しかねている。思わぬチェーンブロックの出現に、あの時の幼きジャックの頭では効果処理が追いつかなかったのだ。目を丸くさせるので精一杯で、やがては時間切れ。you lose。あなたの負けです。
愛の理由も、言葉の意味も、何もかもを全て洗いざらいに説明しなければ伝わらないというのか。気が遠くなるような感覚を(シティとサテライトを一つにつなぐ努力をするようなものだ)(伝説の男になるわけか)、ジャックは今までの生涯の中で、一度たりとも忘れたことはない。そのときに感じた絶望も、くそったれと汚い言葉を吐き散らしたくなるほどの胸糞の悪さも、全部。
そして現在。幼きジャックを絶望の淵に叩き落とした張本にはというと、勝手に彼の住処に上がり込み、壊れかけの古びた冷蔵庫の中をくまなく物色していた。忌まわしい過去を思い出して、虫の居所の悪い彼など御構い無しに、はあーだのうわあだのと声をあげている。
「相変わらず酷い食生活だね。そのうち栄養失調になって死んじゃうよ?」
辛うじて口に含めそうなものと言えば、未開封のミネラルウォーターに、まだ手にいれて新しい食パンくらいだろうか。卵やミルク、加工肉などのある程度の食材なら入っていたような気はしたが、はて、賞味期限はいつまでだっただろうか。サテライトに流れ着く食料の賞味期限にいちいち気を配るなど無意味だったし、当のジャックは腹にさえ入ればそれでいいというスタンスだった。
「人の私生活に首を突っ込むな、鬱陶しい」
「だってあなたテキトーなんだもん。マーサにお願いされてるのよ、ちゃんと食べてるか、生きてるか確認してきておくれって」
は冷蔵庫から牛乳を取り出すと、口を開けて匂いをかいだ。彼女はすぐに顔をしかめて、鼻をつまんだ。
「うわっ、腐ってる!信じらんない!なんでこういつも、様子を見に来るとなにかしら腐ったものがあるわけ?まさか飲んでないよね?」
「ええい、誰が様子を見に来いと頼んだ!マーサの頼みだかなんだか知らないが、文句を垂れるだけなら帰れ!お前に構っていられるほどオレは暇人ではない!」
「本読んでデッキ組んでるだけのくせして、なーにが暇人ではない!よ。つれないなあ、麗しの幼なじみの来訪だってのにさ。もうちょっと、外面だけでもいいから喜んでくれたっていいのに」
なにが麗しの幼なじみだ。心底ばかばかしいと、ジャックは失笑を漏らした。
些細な口論の最中にも、は冷蔵庫内の食材とじっとり睨み合い、匂いを嗅いで状態を確かめ続けていた。まだいける、もうだめだ、と、市場で掘り出し物を探すかのように分けている。が、ほぼほぼアウトのようだ。大体の食材がゴミ袋行きである。
「はあ、使えるのは食パンくらいか。ま、色々持ってきたからいいけどね」
幼なじみというよりも、口うるさい母親のようであった。マーサの影響を色濃く受け継いでいるような気さえした。
ジャックはというと、なんとも言えぬ表情でを見ていた。複雑な心境、腹立たしといえば、腹立たしいかもしれない。手に届かない存在であることを思う存分しらしめたくせに、ちょこまかと周りをうろつくはなんとも煮え切らない態度を取っていると言えよう。ああ。この黒く渦巻く感情をどうしたものか。
腰掛けていた簡易ベッドのの足元には、が訪れてくる前まで目を通していた文庫本が無造作に横たわっていた。それを拾い上げて、ぱらぱらとページをめくる。何ということだろう。どこまで読んでいたのか、すっかり忘れてしまったではないか。こうなってしまっては、また一から読み始めるしかない。
と関わるといつもこうだ。彼女の存在はすごろくの「スタートに戻る」のマスそのものだ。何もかもが無かったことになって、振り出しに戻ってしまう。一歩進んで二歩下がる。最初からやり直し。
どうしてそんな女に、未だ淡い感情を抱いているのだろう。ジャック自身も理解に苦しんでいる。
「ジャック、なに読んでるの?」
「お前には関係ない」
「けちんぼー」
「なんとでも言え」
は目を細めて、アヒルのように口唇を突き出した。ジャックはというと、読書にどうにかしてでも集中しようと善処しているのだが、の姿が視界の端でちらつき、気が散ってしまう。読書どころの事態ではなかった。一挙一動、髪を耳にかけるわずかな仕草にさえ、目線が奪われる。
生ゴミの処理を終えたは、どれどれ、とため息まじりに立ち上がった。ジャックの悪態に腹を立て、帰るのかと思ったが、持参した紙袋から牛乳瓶と卵とバターを取り出しただけだった。簡素なキッチンのカウンターにそれらと、食パン、フライパン、菜箸、ボウルを並べると、はくるりとこちらを振り返る。
「フレンチトースト作るけど、食べるでしょ?」
「勝手にしろ」
「はあい。勝手にします」
はボウルに卵を割ると、牛乳と砂糖を入れてかき混ぜた。食パン二枚をそれぞれ4等分に切り、浸す。熱したフライパンの上では、バターが形なくどろどろと溶けて、鼻腔をくすぐる濃厚で心地よい香りを放っていた。一連の流れるような作業は、ジャックの腹の虫を騒がせ、唾液で口内を溢れ返させるには充分すぎた。そういえば、しばらくまともな食事をしていなかったな。
ジャックは、他人の作った飯に関しては、ああでもないこうでもないと文句を垂れるのが大半ではあるが、の作るマーサ仕込みのフレンチトーストだけには一度も不満を並べた事はない。好きか嫌いかと尋ねられれば、好きと答えるだろう。好物か、と問われれば、迷わず首を縦に振るだろう。
心の片隅で、ふと考える。毎日、が俺の為だけにフレンチトーストを作ってくれたらいいのに、と。毎日はさすがに飽きるか。それ以前に、叶わぬ願いではあるが。
の瞳に映るのは、今も昔も、遊星だけだ。遊星だけを求めて、彼女は生きている。
遊星はみんなの憧れの的だった。それはジャックにとってもそうだった。ライバルであり、友であり、尊敬に値する人物。誰だって同じ考えであるだろう。
は食事の最中、身の回りの近況や、遊星のことを話していた。今取り掛かっているDホイール制作の過程だとか、どこまで進んでいるのかとか、Dホイールに夢中になりすぎて自身の事がおろそかになっているだとか、最近ラリーがデュエルの腕を磨いており遊星を追い詰めたことだとか。
遊星のことを語る時はいつも、誰に対しても見せたことのない淡い色を伴った表情をしていた。幸せそうだと思った。目を爛々と輝かせるその姿はいつもでも、恋をしているように見えた。反対にオレのことを誰かに話すときはどんな表情をしているのかなんて、知る由もない。
一通り食べ終えると、はお喋りに一区切りをつけた。だが、いつもの彼女であればてきぱきと食器とあたりを片付け、満足げにここを去るのだが、今日に至っては終始緩慢な動作であった。一見すると、ここを去りたくないようにも見えた。
「どうした。帰らないのか」
「あ、ううん。ちょっと考え事してただけ」
は左手の腕時計をちらりと見遣ると、うんうんとなにか決心をつけたかのように二回頷いた。
「ねえ、ジャック。よかったら久しぶりに見に行かない?」
「何をだ」
「シティ」
あの、きらびやかなネオンを。
思わず、狼狽えた。からそういった誘いを受けるなど、初めてだったからだ。顔には出さなかったが、ジャックの心の狼狽は、自覚せざるを得ないほど明らかであった。顔に出ないよう、表情を強張らせる。聞き間違いか?いいや、そんなことはない。はっきりと彼女の声は、ジャックの耳に届いている。
「ジャック?」
黙り込んだジャックに、彼女は顔を覗き込みながら問いかける。ジャックは視線を逸らして、自身の焦りを悟られないようクールに気取るのが精一杯だった。
「いいや、遠慮しておく。もう遅いんだ。そろそろ帰れ」
「そっかあ。じゃあ、また今度ね。約束だよ」
彼女の少し残念そうな顔を見ると、少しばかり胸が痛んだが、後々考えてみれば、この時彼女の誘いを受けなくて本当によかったとジャックは思っている。シティのネオンは、サテライト育ちの彼にはいささか眩しすぎるのだ。憧れて止まないあの街の煌びやかさは、年を重ねるたびに、忌々しい劣等感を植え付けてくる。見てるだけで胸が苦しくなるだけだ。こんなごみ溜めから早く抜け出したい。あのネオンに照らされながら、とともに生きていたいという願いが、強まってしまう。
そうしてまた、感情の高ぶりに身を任せて、一世一代の愛の告白をにしてしまっていたことだろう。愛してる。結婚してくれ。ここから出よう。オレと共に生きていこう。なんて。そしてそこで「冗談でしょ?」なんて返された日には、彼の心は修復不可能なほどズタズタに壊されてしまっていたに違いない。
「帰るんだろう。途中まで送っていく」
ジャックは傍のコートを羽織って、に上着を手渡した。はそれを受け取ると、目を丸くさせて、手渡された上着とジャックを交互に見遣っていた。
「え、」
「不服か?だったら一人で……」
「まさか!珍しいなって思っただけだよ。お願いします」
慌ててはジャックの言葉を遮った。外に出れば、一層と肌を突き刺すような寒さが身に染みた。吐く息は白く、ジャックは思わず身を縮こまらせる。ポケットに手を突っ込んで、歩幅も気にせずずかずかと歩いた。「ちょっと待ってってば!」と叫びながら、が小走りで近づいてくる。
「ジャ、ジャック、歩くの速すぎだよ。送ってくれるんじゃ、」
「遅い。置いていくぞ」
「ああもうっ。追いかけっこじゃないんだからさ!」
月明かりだけが頼りの夜道で張り上げられたの声は、瓦礫の街に染み渡るように響いた。ジャックは不思議と気分が高揚した。に気付かれぬよう、口元を緩く歪める。何故だかはわからない。これからは遊星の元へ帰るというのに、悔しくも、苦しいとも感じなかった。ただなんとなく…きっとこれから先も、近づくことも遠ざかることもないであろうとの1メートルの距離が、愛おしく思えたのだ。