もう二年も前の話になる。ジャックと遊星が袂を分かったのは、今思えば運命だったのかもしれない。最初から彼らには、相容れない思想が胸中にあったのだ。現状を受け入れた遊星、現状を抜け出したいジャック。どちらかが間違っているなんてことはない。どちらの思想も正しいのだ。ただ、目指すものが違うだけ。
お互いの主張がぶつかり合って、完全なる亀裂を生んだのが、あのデュエルだった。
「勝利を築き上げるために最も必要なものは、ここにある」
胸に拳を当て、勝者は敗者に告げる。地に這いつくばり、拳を叩きつける遊星と、それを見下ろすジャック。二人の因縁の対決は一度、決着がついた。
だがそれはデュエルでの話だ。
の所有権がどちらにあるのか、という、水面下の争いは未だ、二年経った今でも、決着がついていない。もちろんも、そんな諍いが水面下で行われていたことなど、知る由もない。
「ジャック…遊星…」
閉じ込められたコンテナの中で、は祈るように呟く。昔のように、みんなで、笑顔で過ごせるようになりますようにと、願いを込めて。
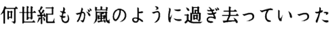
しばらくの間、変わらない日々が続いた。仕事と生存確認。それがにとっての生きがい。廃れた街に輝く、人生の一筋の光。敷かれた光のレールに沿って生きる。幼なじみたちの元気そうな姿を見て、遊星の鼓動に包まれながら眠る。壊したくない日常が、そこにはあった。
遊星は相変わらず無茶な生活を自身に強いていたが、最低限の睡眠と食事を諭せば彼はおとなしく言うことを聞いた。幾度とない失敗を繰り返して、歪だったDホイールは徐々に形を成していった。モーメントエンジンの制御も、デュエルシステムの導入もチューニングも済ませた。第一回制御テストと称した試験走行には、ジャックも顔を出した。壁にもたれかかって、ラリーたちの期待に満ちたかんばせを遠巻きに見つめていた。
そして瓦礫の街に、星屑の龍が舞った。雄大な翼を羽ばたかせる姿は美しく、雄々しく、その側面で儚ささえ感じさせた。自由の象徴、それがDホイール。自由を求める男たちの驚嘆の声が辺りに響く。みんなの夢が叶った瞬間だった。
途中、ソリッドビジョンシステムにエラーが起き、結果としては失敗に終わったのだが、遊星は何かを掴んだようだった。基本的に感情をあまり表に出さない彼が珍しく、満足げに顔を綻ばせていたのだ。タカやナーヴはハイタッチを求め、ブリッツは遊星の肩を抱き、ラリーは目を爛々と輝かせて遊星を褒め称えた。
凄い、凄いよと、誰もが遊星を崇めた。
の心境は複雑なものだった。遊星の努力が実を結んだ結果は、当然ながら嬉しかったし、喜ばしいことなのだが、その反面、彼もまた自分の手の届かない場所へ行ってしまうのではないかという一抹の不安は決して拭えるものではなかった。サテライトの希望の星は、果たしてサテライトの中だけで満足していけるのだろうか。ジャックのように、外の世界を渇望求めてしまうのではないか、と。
「……フン」
切なげな面持ちのを横目に、ジャックは表情ひとつ変えずにいた。盛り上がる彼らに背を向ける。今すぐにその場を離れたくて仕方がなかった。に名を呼ばれ、どこへいくの?と聞かれたが、返事はしなかった。
奴にあって、オレにないもの。オレにはあるのに、奴にはないもの。明確に存在する思想が、相反する。の熱い視線を独り占めにする遊星が憎くて憎くて仕方がなかった。見るための目と、聞くための耳と、話すための口がある。全部バラバラだ。繋がっていない。ひとつながりのはずが、いくつもあるようだ。アイデンティティーが崩壊する…オレの存在理由はなんだ?何が嬉しくて、今を生きている?
見つからない答えを求めて、思考が脳髄を這いずりまわっている。生まれた時から放り込まれた深い井戸の上空には無限の可能性がいくつも飛び交っているのに、いくら手を伸ばしたって届きそうにもない。ただ恨めしそうに、指をくわえて見ていることしかできないのだ。
「出かけてくる」
後日、の訪問があった。大量の食料を抱えてやってきたのだ。ごく稀に彼女は、保存用に食料を大量にこしらえる時がある。作り込んだ食料はかろうじて機能している冷凍庫に保存される。彼女が作り置きをする…それは「しばらく訪問できない」ことを意味していた。どうせ遊星がらみだ。ジャックはそう思った。虫の居所の悪さに居た堪れなくなって、ジャックは部屋を飛び出した。不審そうに見つめるの視線がジャックの背に集まる。構うもんか。
崩れた雑居ビルの中をふらふらとあてもなく彷徨っていると、外から聞き馴染みのある声と、荒れくれものたちの言い争う声が聞こえた。
「逃げろラリーちゃん、でないと痛い目に合わせるぜぇ!ハハハ!」
見やれば、三人の荒れくれものに追われているラリーの姿があった。まだ未熟な短い足を懸命に動かして、必死に逃げている。一人の男はバットを手に持っていた。ラリーがその場に勢い良く転んでしまうと、バッドの男はニタニタと笑いながら頭上にバットを振りかぶった。容赦なく、小さな体躯に振り下ろそうとしている。
考える暇もなく、ジャックはデッキからカードを引き抜いて、手裏剣のようにバットを持つ男の手元に投げつけた。カードは回転しながら美しい直線を描き、男の手元にクリーンヒットする。突然の出来事に男はバットを手放して、痛みが走る掌を押さえつけながら、驚いた様子で起き上がるラリーを睨んでいた。
「てんめぇ、何しやがった!」
「えっ……、ジャック!」
思いもよらぬ助け船を出した、頭上に君臨するジャックの姿に驚いて、ラリーは叫んだ。ジャックは持ち前のアメジストの瞳で冷ややかな視線を余すことなく目下の男たちに送っている。当の荒れくれものたちも、予期せぬ出来事と、彼の放つ冷ややかな視線に狼狽えていた。
「ここが誰のフィールドか分かってるだろうな」
その場から地に降り立ち、ジャックは言い放つ。ラリーが勢い良く駆けてきて、ジャックの後ろに身を隠した。じりじりと男たちは後ずさりをする。
「俺はなにも…アンタに喧嘩を売るつもりなんて…」
「ここではオレがキングだ。お前の御託は後で聞いてやる!」
デュエルディスクをセットし、カードを引き抜く。召喚されたのは、レッドデーモンズドラゴンだった。けたたましいドラゴンの咆哮は、あっという間にフィールドを支配する。男たちは悲鳴を上げながら勢い良くその場から逃げていった。
「へっへー!この腰抜け!一昨日きやがれ!」
ラリーは虎の威を借る狐のように、拳を振り上げて、男たちが逃げていった小道に向かって叫んだ。どうだ、まいったか!ほんの数秒前とはうって変わって、怯えていた瞳には自信が満ち溢れている。
「…あれ?」
振り返ると、既にジャックの姿は無かった。何事も無かったかのように、辺りは静寂に包まれている。
ジャックがどこにいるのか、大体の見当はついていた。扉の隙間から顔を出せば、玉座に腰を据える王者の姿があった。予想通りだ。ラリーは無邪気な笑みを浮かべながらジャックの元へ小走りに駆け寄った。
「何の用だ」
放たれた言葉は冷たく、拒絶と敵意に満ちていた。
「さっきの、礼を言いたくてさ」
「オレは自分のフィールドを守っただけだ」
ラリーは耳の穴に小指を突っ込んで、眉間にしわを寄せた。最近のジャックは様子がどこか違う。とっつきにくさが前面に押し出されているのだ。何て言葉を繋げよう?ラリーの視線は空を泳いだ。
「あ、あのさ!今遊星のDホイールを再チューニングしてんだけどさ、明日もう一回試験走行するんだ。……ジャックもまた来なよ!信じられないくらい、この間よりバカっ早いんだぜ!」
どんなに言葉を投げつけても、ジャックの視線はラリーを捉えることはない。反応を示さないジャックにむっとして、ラリーはジャックの視界にどうにか納まろうと、玉座の前に歩みを進める。
「俺たちずっと仲間だったじゃん。前みたいにみんなとデュエルしようよ!」
ラリーの力説にも、ジャックは顔色ひとつ変えることはなかった。
「ジャック……」
「オレと奴とは違う」
「何があったの…遊星と」
「ただ違うんだ。目指すものがな」
思いつめたように、ジャックは吐き捨てる。全てを悟り、諦めているようにも見えた。嘆き、怒り、苦しみ。全てが集約されたようなセリフだった。
「俺は…!ただ、二人には仲良くして欲しくて…。だって二人とも同じサテライトの希望なんだからさ!」
ジャックは眉ひとつ動かさず、黙って彼の言葉を聞いていた。痺れを切らしたラリーは身を翻して、腰に手を当てて言う。
「じゃ、じゃあさ、気が向いたら見に来なよ。それじゃ!」
勢い良く駆けていくラリーを横目で見送る。遊星は同じ過ちを繰り返すほど愚かな男ではない。今度こそDホイールは完成すると言っても過言ではないだろう。ジャックは玉座に座ったまま項垂れた。遊星は明日、自由を手にする。風と一体になって、サテライトを走り抜ける。ジャックが求めるものとは違う「自由」を、己の手で成し遂げ、手に入れるのだ。…そうしたらきっと、の視線は遊星に奪われたままで、取り返しのつかない事になるだろう。
そうなったらもう、どうする事もできないと、諦めるしかないと思った。今、住処に戻ったとしても、きっとがいるだろう。捨てきれない感情が、胸中を渦巻く劣等感が、ジャックの体を強張らせる。
(オレは…ここから動けないんだな、後にも先にも、ずっと)
いつの間にか眠りに落ちていたようだ。既に日は落ち、満月が割れた天井から光を惜しみなく注いでいた。
こつこつ、と革靴が地を叩く音があたりに響いた。虚ろだった瞳が覚醒する。
「誰だ!」
ジャックは立ち上がって叫ぶ。数歩進み、辺りを見渡すも、人影はない。
「初めまして、ジャック・アトラス」
振り返ると、足音の主が玉座の陰から姿を現した。「わたくし、イェーガーと申します。治安維持局長官、レクス・ゴドウィン様の使いで参りました」
彼は瞼を閉じ、丁寧に深々とお辞儀をしてみせた。まるで敬意を示すかのような行いに、ジャックは訝しみ、眉間にしわを寄せる。
「治安維持局が何の用だ」
「貴方をシティにお誘いするようにと…」
シティに、だと?予想だにしない単語に、ジャックははっと目を見開く。
「長官は、シティに君臨する王が必要だとお考えなのです。王の存在はシティの象徴として、市民に夢と希望を与える。ひいてはシティの発展と治安維持に繋がると」
イェーガーはわざとらしい身振り手振りを交えながら続ける。
「その役目を貴方にやって頂きたいのです。何より、その右手の痣こそが王の印。ヒッヒッヒッヒ」
ジャックは驚いた面持ちで指をさされた右腕に視線を移した。なぜ、初対面だというのに右腕の痣の事を知っているのだ。
「明日の夕方五時、一時間だけパイプラインの流出が止まります。我々には貴方を迎え入れる準備がある。しかし、シティへのパスポートとして必要なものが二つ」
断りもなく玉座へ座り、足と手を組んで、イェーガーは話を進める。ジャックの胸中など御構い無しだ。
「それは、レッドデーモンズとスターダストのカード」
「……!!」
「もちろん、貴方がスターダストを持っていないことは承知しております。ですが、その二枚が必要なのです。カードの入手手段は問いませんがね」
張り詰めた空気が辺りに漂う。だが、ジャックにとってイェーガーの誘いは救いの手とも言える代物だった。彼が提示した、シティのキングになる為に必要なもの。それさえ手に入れてしまえば、この忌々しいごみ溜めから抜け出すことができる。
「ジャック。貴方が信じるか否かは自由。ですがよくお考えください?チャンスは一度きり。このままスラムのキングで終わるか、それとも本物のキングとしてシティに君臨するか。それは貴方次第…」
イェーガーはまた不快なほど不気味な笑い声をあげた。思いふけるように視線を落とすと、汚らしい触覚を生やした生き物がかさかさと足元に寄ってきていた。
「では、いずれシティで」
視線を元に戻せば、イェーガーの姿は玉座から忽然と消えていた。どこからともなく別れの言葉が送られる。まるで、ジャックがシティへの切符を必ず手に入れ、再び会えることを確信しているような口ぶりだった。
「ああ、それと…告げておかなければならないことがもう一つ」
出処のはっきりしないイェーガーの声は遠ざかってはいたが、その声ははっきりとジャックの耳元へ届いていた。
「貴方の気がかりであろう、と云う女…彼女はなかなかしたたかな女ですね。いくら思い焦がれてもその気持ちは成就することは無いでしょう…。なぜなら彼女は毎晩、あの不動遊星と云う男と床を共にするほど仲が良いみたいですからね…ヒッヒッヒ」
「…なんだと?」
「おっと。これ以上はわたくしの口から申し上げるより、本人に問いただしてみた方がいい。では、失礼」
「待て、貴様、どういうつもりだ!」
張り上げた声は、虚しく瓦礫の街に響き渡るが、返事はなかった。シティへ行けるかもしれない。遊星とが、自身の予想を遥かに跳躍した関係にまでなっているのかもしれない。葛藤、欲望、絶望、全てがぐちゃぐちゃに混ざり合っている。行き場のない怒りと期待だけがここに取り残されている。
心臓の鼓動が煩い。血液が沸騰したみたいに、体が熱い。ジャックは行き場のない怒りに身を任せ、片足を振り上げて、足元をうろつく黒い塊を踏みつぶした。
ジャックの心は、荒れた海のように激しく揺らいでいる。必要なものは、Dホイールと、スターダストのカード。それだけ。
イェーガーがなぜ去り際に、あんな胸糞悪いだけでしかない情報を教えてきたのか、その理由は明白だった。彼が迷いなくシティに赴く為には、足枷を取り払ってやらねばならないからだ。
ジャックは足の裏にこびり付く不快な感触を拭うように、地に靴底を擦り付けながら帰路に着いた。荒々しく自室の戸を開ける。自室では、がベッドの縁に腰をかけて本を読んでいた。どうやら、帰りを待っていたようだ。
「お、おかえり。どうしたの、ジャック、そんな怖い顔して…」
澄ました顔で、そんなことを言ってくる。オレが何も知らないとでも?出来ることなら、知りたくなかった。耳にしたくなかった。考えたくもなかった。行き場のない怒りは、あの黒い塊を踏みつぶしたところで収まるはずがない。
ジャックはの読んでいた本を勢い良く奪い取ると、それを投げ捨てた。激情は止まることを知らず、正常な思考を振り払って突き進むばかりだ。彼女の胸ぐらを掴んで腰を浮かせれば、彼は力任せにを押し倒した。
「痛っ…!じゃ、ジャック?なに、どうしたの、ねえ」
「寝食を共にしているのは知っていたが、同じ床で寝るまでの関係だったとはな。奴とはどこまで進んだ?奴と何をした?オレを翻弄して楽しんでいたのか?!言え、言ってみろ!」
荒々しくジャックは捲し立てる。出て行く前とはうって変わって、激しい激昂を見せるジャックには目を白黒させるばかりだ。なぜそれを、と言わんばかりに口をポカンと開けて、肩を震わせている。
「お前はいつもそうだ。何もかも忘れて、何も無かったように振る舞う。オレがどんな思いでお前を見ていたか、分かっているのか?!」
小細工なんてもう必要ない。妥協も、優しさも、見せる必要もない。ジャックはの顎を掴んで、口付けを施した。がつん、と歯と歯がぶつかり、鉄の味がお互いの口腔に広がる。
「っ…や、待って!ジャック!」
は顔を背け、両手で彼の胸を押し返して拒絶の意を露わにした。ジャックは彼女の拒絶を拒んだ。の両手首を掴んで、彼女の自由を奪う。か細いは男の力に敵うはずもなく、足をばたつかせることしか出来なかった。組み敷かれ、ジャックの怒りに、ただただ戸惑いの色を浮かべるばかりだ。
「シティを見に行こう?お前は、最後にあのネオンを見に行った日のことを、覚えているのか?覚えていたのに、あんなことを言ったのか?」
「お願い、ねえ、離して…」
「オレの気も知らないで、こうやって、犯そうと思えばいつだって出来たんだ。そうしなかったのは何故だか、お前に分かるか?!」
思いの丈を言葉にして、ぶつける。怒りだけが彼を支配し、突き動かしていた。手首から手を離し、のブラウスのボタンを引きちぎるように外していけば、の顔色は瞬時に青ざめていった。
「い、いや!止めて!ジャック!」
腕の中でもがく彼女の目尻には涙が浮かんでいた。瞼をぎゅっときつく閉じて、暴れる。ジャックの手首を掴んで、制止を求める。
「私は遊星と、こんなことしてない!あなたが思っているような関係じゃない!!」
「だからどうした!オレはお前が好きだ、お前を愛しているんだ!ずっと昔から!どうして分からない、どうしてこの言葉を、冗談だなんて思うんだ!」
ジャックの指がブラウスの最後のボタンを外すと、白く骨ばった上半身が露わになった。下着を荒々しく捲くし上げれば、小さな胸と淡い色の乳首が露出する。
ぱん、と乾いた音が響き渡った。そして、静寂。それと、沈黙。ジャックの頬がじんと熱を持った。頬を叩かれたと気づいたのは、数秒後だった。
「最低」
はジャックを振り払い、起き上がって下着を直しながらそう言った。ブラウスの首元を掴んで肌を隠す。瞳を潤ませ、ぼろぼろと涙を流している。彼女は追撃する。ジャックを睨みつけてもう一度「最低」と言い放った。軽蔑するような視線が、ジャックに突き刺さる。
鞄を拾って、は逃げるように勢い良く部屋を飛び出した。荒々しい足音が、遠ざかっていく。取り残されたジャックは、拳を振り上げて、自身の頬を殴った。
やってしまった。押さえ込んで、蓋をしてきた感情が、全て流れ出てしまった。吐き気を催すような気分の悪さがジャックを蝕む。
ここは地獄だと思った。息が詰まりそうなほどの退屈も、乾きも、憂いも、もうたくさんだ。