私は感情で見つめているのに
お前とは会話にならない
思想がない。感情だけだ
違うわ。思想は感情にあるのよ
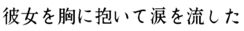
ジャックを襲うアイデンティティ・クライシスは崩壊を辿る一方だった。後悔と自責の念が、胸中でどす黒く渦巻いている。酷いことをした。許される所業ではないと分かっていたからこそ、ずっと隠して、理性を働かせ、押さえ込んできたというのに。
どうすることもできなかった。例え遊星と暮らしているとしても、心のどこかでは諦めがつかず、もしかしたら付け入る隙があるのではないかと思っていた。だが、現実はそんなに甘くないのだと、打ちのめされる結果ではあったが。
「大馬鹿ものだな…オレは」
はきっと今頃、ジャックの豹変した姿に怯え、泣きじゃくっていることだろう。そして、優しい、愛しの遊星にありのまま起こったことを話して、慰めて貰っているに違いない。きっとそうだ。そうに決まってる。
「スターダスト、か」
傍に置いたデッキからレッドデーモンズのカードを取り出し、呟く。後悔と自責の念で押し潰されそうな今でも、奇妙な道化のメイクを施した小柄の男が放った言葉が、幾度となく脳内でリフレインしていた。
手の届きそうになかった野望が現実味を帯びて手中に収まろうとしている。恋い焦がれた夢が現実になる瞬間が、きっかけが目の前にある。遊星がDホイールを作り上げたように、オレはオレなりの自由を手に入れられるだろうか。例え仲間や故郷を裏切る結果になったとしても。
荒廃した地下鉄に戻ると、既に遊星は寝静まっていた。明日の試験走行に向けて体力を温存しておきたかったのだろう。それに、日々の疲れも溜まっていたのだろう。甲高く響く足音に気づきもせず、すやすやと寝息を立てている。は彼を起こさないよう足音を忍ばせながら、蛇口を捻った。未だ止まりそうにない涙を引っ込ませようと嗚咽をぐっと堪える。
息が切れ、目の前が霞むほど走るなど、いつぶりだろうか。涙と鼻水でぐちゃぐちゃの顔面を洗いながら、はふと冷静に考えた。
マーサハウスにいた頃は、一緒に暮らしていた幼なじみたちと、来る日も来る日も飽きることなく息が絶え絶えになるほど遊んでいた。デュエルだってそうだ。声が枯れそうになるくらい大はしゃぎして、勝敗に一喜一憂し、デッキの構成を考えては新しいカードが流れ着いてこないかとみんなでジャンクの山を漁ったりした。あの頃は先のことなど考えず、ただ毎日が楽しくて仕方がなかった。
歳を重ねるごとに、自身のノスタルジーが加速していくのはなぜだろう。みんな前に進んでいる。確かな未来を求めて、歩を進めている。誰にだって夢はある。野望も希望も、同様に。それらを胸に抱いて、皆明くる日も汗水垂らしながら生きているというのに、自分は未だ過去に囚われ、縋り、生きている。
「友達のままじゃいられない…か」
顔に付着した雫がぽたぽたと地に落ちる。ジャックが吐露した心情は、の心をかき乱すには十分すぎた。ジャックの著しい変化も激昂も、頭のどこかではいつか来ると分かっていたことなのに、いざそれを露わにされると、拒みたくなる自分がいる。
太陽は沈み、また日は昇る。変わらない日常が毎日繰り返されているはずなのに、人間は成長し、自我を持ち、変化していく。きっとこのサテライトで変化を求めていないのは自分だけなのだ。
ずっと、あの時のままでいられたらなんて、おこがましいのだろうか。この世に正解なんて、存在しているのだろうか。私はずっと、過去という檻に囚われたまま、歩き出すことができずにいる。
どんよりとした暗い雲が上空を覆っていた。まるで、ジャックの胸中を具現化したような天気だった。サテライトとシティを見渡せるほどに高い建物の屋上で、ジャックは人を待っていた。
「どうしたの?俺に頼み事って…」
待ち人はラリー・ドーソンだった。人懐っこく小走りで駆け寄ってくるラリーとは反対に、ジャックは興味も示さず、振り返りもしなかった。ポケットに手を入れたまま、コートの裾を風に靡かせている。
「オレは…ここを出て行くことにした」
「マジ?!でも、どうやって?」
ラリーは驚いた様子だったが、その顔には笑みが讃えられていた。
「それにはお前の協力が必要なんだ」
「俺に出来ることならなんでもするよ!」
「……そうか」
無邪気に喜ぶラリーは、疑うことを知らない。まだ子供なのだ。仕方のないことだとはいえ、ジャックの良心が今更痛むことなど無かった。ようやくジャックは振り返ったかと思えば、無慈悲にも一撃を食らわせ、ラリーの気を失わせた。脱力し、体の支えを一気に失ったラリーは、ジャックの腹にもたれかかって、そのまま地に伏した。
試験走行までまだ時間があるということで、は買い出しに出ていた。今日はきっと、特別な日になるだろう。なにかご馳走を作って、みんなでパーティをしようと思い至ったのだ。なけなしのお金を財布に忍ばせて、何を作ろうかと考えを巡らせる。なにかをしていないと、昨日の夜の出来事がまざまざと蘇って、遊星らの前で泣いてしまいそうだった。
サテライトの市場で特別な食材を手に入れるのは至難の技だ。ケーキを作るための生クリームや、甘味などはそれこそ入手しにくい。しかしパーティといえばケーキ、とは思っている。かぼちゃでも買って、それらしくなるように作ってみようか。
そう考えている時だった。!と叫ぶブリッツの声が、思考を停止させた。
「おい、!ラリーが攫われたんだ!探すの手伝ってくれ!」
息を切らし、額から汗をだらだらと流しながらブリッツは言う。
「ラリーが?誰に?」
「それは分からない。さっきジャックから遊星に通信が入ったんだ。何者かに攫われたって」
じゃあ頼んだぞ!と言い残して、ブリッツは走り去っていった。背筋が凍る。胸騒ぎがする。なにか良くないことが、起きようとしている。
遊星とは幼い頃から何度も何度も、数え切れないほど戦っていたというのに、あの時のデュエルだけは、二人にとっても、周りにとっても特別なものであったことは間違いない。
勝者は敗者を意のままに出来る、なんて事はない。お互いの力を全て出し合い、己のプライドをかけて戦ったが、勝敗に白黒をつけ、亀裂を生んだだけで、水面下の争いなどは結局、当人が決める問題なのだ。
「遊星。デュエルとは、モンスターだけでは勝てない。トラップだけでも、マジックだけでも勝てはしない。全てが一体となってこそ意味を成す」
悔しそうに地に這いつくばる遊星に向けて、ジャックは説き伏せる。
「そして、その勝利を築き上げるために最も必要なものは、ここにある」
それが何なのかは明言しなかった。真のデュエリストならば、言葉にせずとも理解できることだから。
ジャックは遊星が海に飛び込む際に残していったデッキケースからスターダストのカードを抜き取る際、そんなことを思い出していた。遊星とはあの時、デュエルを通して分かり合うことが出来ただろうか。思想が違い、目指すものが明確に違う者同士、デュエルで語り合えたのだろうか。
ジャックの答えはノーだ。分かり合えない。分かり合えやしない。そもそも、分かり合いたくないのだ。
「遊星!!!」
荒れる漣の音に紛れて、愛しい女の声がする。こんなにオレが近くにいるのに、は遊星の名を叫んでいる。
そうだったな、とジャックは思いふける。遊星と決別したあのデュエルの時も…が真っ先に駆け寄ったのは遊星だった。
オレは単なる傍観者で…ただの仲間に過ぎなかったのだ。
攫われたとはいえ、どこを探すべきなのか見当もつかなかったのに、あの場面に出くわす羽目になったのは、運命の悪戯だと思わざるを得なかった。神様がいるならば、なぜ、どうしてと責め立ててやりたい。はいつになっても、あの情景を思い返すたび運命を呪いたくなる。
ラリーを探して海辺の道路にたどり着いたのは、遊星がジャケットとデッキケースを投げ捨てて海に飛び込む瞬間だった。荒れ狂う海をかき分けるように無我夢中で泳ぎ出した遊星の姿に、は彼の名を叫ばずには居られなかった。
「遊星!!!」
道の淵まで駆け寄り、遠くを見渡せば、遊星が進む先に小型のボートとロープでぐるぐる巻きに縛られたラリーの姿がある。なぜ?どうしてこんなことに?は状況が理解できず、呆然とした表情でジャックを振り返った。
「全てオレが仕組んだことだ」
思いがけないジャックの言葉に、は狼狽した。ジャックに詰め寄って、服を掴み、揺さぶる。
「どういうこと?何を言ってるのか、全然分かんないよ!」
「…去る前に、お前には謝らなければならないな」
ジャックは狼狽えるを冷徹なまでの冷ややかな目で見下しながら、そう言った。
「昨日はすまなかった」
無論、この言葉はが求めるレスポンスでは無かった。焦りと狼狽が彼女を支配している。どうしてこんな状況に陥っているのか、ただ説明が欲しかっただけなのに、ジャックは昨日の話をしている。会話が成立していない。もどかしさが募った。
「そんなことどうでもいいよ!それより、遊星が…!」
ジャックの中で、ぷつん、と何かが事切れる音がした。アメジストの冷ややかな瞳は、一瞬にして熱を持つ。服を掴むの手を乱暴に振り払い、ジャックはありったけの力を込めて怒鳴った。
「遊星、遊星、遊星遊星遊星!!!!もううんざりだ!!」
よろけるの胸ぐらを掴み返して、ジャックは続ける。
「そんなことだと?お前にとって、昨日のあの出来事は”そんなこと”程度のことだったのか?!」
「ジャック、ちが、」
「お前はいつも遊星のことばかりだ。お前の心に、オレは居ない。オレを一度も見ようとしない。見てくれやしない!オレはお前を愛している…いや…、愛していたんだ。何よりもお前が欲しかった。お前の側にいられたら、それだけでよかったんだ」
泣きたくなるほどの衝動が、喉元からせり上がっていた。言葉を繋げることすらも苦しく感じた。尖る声が、を次々と責め立てる。冷たい言葉が針のように次々と彼女の体を突き刺している。何も言い返す言葉が見つからず、は唇をわなわなと震わせることしか出来ない。
「これ以上、苦しめないでくれ。ただ黙って愛させてくれないのなら、オレの前から消えてくれ」
非難を含んだ語勢は止まることを知らない。心の根底にある言葉を、今一番伝えたい言葉があるのに、魚の小骨のように喉にひっかかって出てきやしない。オレと一緒に来い。たった一言、この言葉が言えたなら、言えるだけの勇気が、なぜ自分には無いのだろう。
「もう二度と口にするな」
さよならだ。ジャックがそっと胸ぐらから手を離せば、は力なくその場に座り込んだ。大粒の涙が彼女の頬を伝う。泣くな。泣いてる場合じゃない。泣くより、言葉で伝えなければ意味が無いというのに、の声は声にならず、空を切る。下唇をぐっと噛んで、涙を堪えようとしても、涙は止まることを知らぬかの如く溢れ出てくる。
「二度と、オレの名を口にするな」
祈るような口調で、ジャックは囁いた。傍らに落ちていたヘルメットを被り、Dホイールに跨る。エンジンを起動すると、Dホイールが唸った。は「待って」と絞り出すように声を出すも、その声は無残にもエンジンと波の音にかき消される。ジャックは振り返ることなく、その場を後にした。
永遠の刻が流れたかのような感覚だった。ほんの数分の出来事だったというのに、まるで夢の中にいるような感覚さえ覚えた。これが夢ならば、どれだけ幸せなことだろう。頭の中がぐちゃぐちゃだ。どうしてラリーが縛られて海に投げ出されている?どうして遊星とジャックが一緒にいた?どうして遊星が海に飛び込んだのだ?どうしてジャックは遊星のデッキーケースからカードを抜き取っていたのだ?どうしてジャックは、遊星のDホイールに跨って、姿を消してしまったのだ?どうして私はジャックを引き止められなかったのだ?
分からないことだらけだ。
「!!!」
張り上げられた呼び声に、意識が現実に引き戻される。立ち上がって、目をごしごしと擦って涙を拭う。声のする方へ駆け寄れば、海面には今にも溺れそうなほど弱り果てた遊星と、苦しそうに顔を歪めるラリーの姿があった。
「頼む、手を貸してくれ!」
無我夢中で身を乗り出し、手を伸ばす。まずはラリーを引き上げて、その後遊星の手を取り、地上へ引き上げた。遊星は荒れる息を整える間も無く、ラリーの元へ這い寄り、縄を解いてやった。
「ごめんよ、遊星…俺のために…」
デッキケースを拾い上げる遊星に、ラリーはジャケットを手渡しながら謝罪の言葉を述べた。気にするなといわんばかりに遊星はラリーの背をぽんぽんと叩いている。
「帰ろう。みんなが心配してる」
遊星の口調は起きた事件を忘れさせてしまいそうなほどに穏やかで優しいものだった。未だ虚ろな瞳のままのとは反対に、その表情はとても穏やかで、慈愛に満ちている。身に起きた不幸の当事者だというのに、負の感情さえ微塵も感じさせることはない。泣きたくなるような思いをしているのは遊星のはずなのに。どうしてそんなに彼の心は強いのだろう。
「…?」
塊のように動かなくなったを見て、怪訝そうに遊星は問う。
「どうして、泣いてるんだ」
泣いている?私が?は自身の目元にそっと手を添えると、指先にさらさらとした水滴が付着した。あろうことか、二人を引き上げる際に止めたはずの涙が、再び溢れ出している。嗚咽もなく、ただただ静かに涙は頬を伝い、顎先から滴り、コンクリートを濡らしていた。
「……あれ、おかしいな」
泉のように延々と湧き出る涙は、何度拭おうとおさまることはなかった。やがて、は悟る。この涙はきっと、いかなる時も気丈に振る舞う遊星の心と、全てを捨て自分のために生きたジャックの心が反映されたのだと。