もう何度も幼い頃の夢を見ている。サテライト、シティ、ネオン、ジャンクの山、それからジャックと愛の告白。鮮やかで、美しい夢だった。
いかに自分が身勝手で恥ずかしい女であるかなんて、頭の中では理解していた。シティのネオンに照らされたサテライトの端っこで、幼い頃のが言い放った言葉が、ジャックにとってどれだけ残酷で、無慈悲で、非道い仕打ちであったのかなんて、想像に容易いことだったのだ。
「シティを見に行こう?お前は、最後にあのネオンを見に行った日のことを、覚えているのか?覚えていたのに、あんなことを言ったのか?」
これに対する答えはイエスだ。はしっかりとあの日の出来事を覚えている。彼が言い放った愛の言葉「オレがキングになれたら結婚してくれ」も、同様に。あの時、がシティを見に行こうと誘ったのだって、遊星がDホイールに夢中で、自分を見てくれなかったからだ。ラストスパートだと言わんばかりにDホイールに熱をあげる遊星から目を逸らし、ただ自分だけを見つめてくれるジャックに逃げたのだ。
とことんずるい女だと、自分のことながら辟易せざるを得ない。
シティは手に届かないものであるからこそ美しいと思っていた。手に入らないからこそ、綺麗だと思えた。だからこそマーサの目を盗んで、夕暮れ時にジャックと共に、ジャンクと瓦礫で踏場のない道をかき分けて、幼い足を必死に動かしてはあのネオンを見に行っていたのだ。
ただ、ジャックは違った。いつもジャックは野望を秘めた目であのネオンを見つめていた。いつか手に入れてやる、自分のものにしてやると、彼の目は日を追うごとに確かな目標を掲げていた。は幼いながらも、ジャックの秘めたる思いをひしひしと感じ取っていた。
(私はあの時、キングになれたら結婚してくれって言われて…)
夢の中では、幼い頃の自分の姿を遠くから見つめていた。ジャックが、何かを決心したかのように彼女の方へ振り返って、言葉を発している。
(みんなと楽しく生きていければそれでいいって思ってた。変わるのが怖かったから)
幼い頃のが苦笑する。ジャックの顔が、みるみるうちに青ざめていく。
(だから私は、冗談でしょ?って言って、誤魔化したんだ)
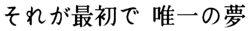
落胆と怒り。遊星を取り巻く仲間たちは複雑な思いを胸中で収めることなどできなかった。それぞれがジャックに対する不満を口にした。罵詈雑言は当たり前。みんなの夢と希望と、自由の象徴を奪われたショックは計り知れないものだったのだ。
事の顛末を遊星から聞いたは、ジャックの行動の原理を瞬く間に理解し、誰よりも深いショックに見舞われた。みんながジャックの自分勝手な行いに怒りを覚え、彼を責めたのに対し、だけは自分のせいだと己を酷く責めていた。
日に日に言葉数も減り、目的も当てもなくふらふらと瓦礫の街を徘徊し、そうしてたどり着くのはいつもジャックの住居だった。忽然と姿を消したジャックの住居はありのままの生活感を残したまま現存していた。唯一無いものは、デッキと彼の姿だけ。
ジャックの匂いが染み付いたベッドに寝転がると、自然と涙が溢れた。彼の居ない部屋は重たく、たくさんの人の冷ややかな視線が集められたような、静かな怒りに満ち溢れていた。もうここに居ない彼の姿を想い、自己嫌悪と罪悪感にまみれながらは眠りにつく。見る夢はいつも決まって、幼き頃のかけがえのない思い出だった。
「」
自分の名を呼ぶ優しい声が、夢の中で木霊する。聞き覚えのある、愛しい声色が眠りから覚醒へ誘っている。
「、また泣いてるのか」
ゆっくりと滲む瞼を開けば、そこには心配そうな面持ちで顔を覗き込む遊星の姿があった。彼は人差し指での涙の跡をゆるやかに辿ると、そっと目尻を拭ってやった。
「ゆう、せい…」
「…俺の前では泣かないんだな」
「心配、かけたくなかったから…」
上体を起こし、は手の甲で涙を拭う。
「一番辛いのはきっと、遊星だもの」
「そんなことはない」
「そう…なのかな」
いつもなら遊星の言葉を全て信じ込んでいただが、情緒不安定な今となってはどんな言葉も彼女の心には響いてこなかった。優しさも慰めも受け止める事ができず、手のひらから砂のようにさらさらとこぼれ落ちていく。
「私ね…夢を見るの。ここに来て、眠りにつくと、いつも同じ夢を見る。何度も何度も…まるでジャックが訴えかけて来ているみたいに」
遊星はの隣に浅く腰をかけると、穏やかな手つきで彼女の肩を抱いた。は凭れかかるように遊星の肩に頭を預けて続ける。
「その度に思い知らされる。私はあの時、ジャックに、なんてひどいことをしてしまったんだろうって」
口唇が震える。止めない涙が両目から沢山溢れ出てくる。涙に誘発されるように、押さえ込んでいた気持ちが、言葉となってお腹からせり上がってくる。
「私ね……私がね……、ちゃんと、ジャックと向き合っていたら、ジャックの気持ちを尊重してあげていられたら、こんなことに…」
「、自分を責めるな。誰のせいでもない。もちろんお前のせいでもない。遅かれ早かれ、きっとこうなっていたんだ」
彼は一貫して、誰に対しての不満不平を述べることはなかった。遊星の慈悲深き愛は、誰にだって平等なのだ。折角多大な苦労をかけて作り上げたDホイールを、夢のスターダストを奪われ、全てが徒労と化した今でも、彼は怒り狂うこともない。ただ黙って、ありのまま起きた事象を享受するだけだ。
「また、作ればいい。一度やり遂げられたのなら何度だってできるさ。みんなの力があれば、難しいことじゃない」
「遊星、私は…」
「もう何も言うな」
遊星はを抱き締めると、あやすように背中を撫でた。長らくの間遠ざかっていた心音が聞こえる距離で、はしとしとと涙を流した。鼓動は一定のリズムを刻み、子守唄のように張り詰めた空気を和らげていく。
「新しいDホイールは前よりも速く走れるように作ろう。色ももっと個性がでるような…何色がいいだろうか…」
「赤、とか、どうかな?」
「そうだな、そうしよう」
遊星は囁く。また手伝ってくれ、と。は遊星の腕の中で頷いた。
「キングは一人、このオレだ!」
パソコンの画面の向こう側で、Dホイールに跨り、天を指差し、高らかに勝利を宣言する男を、たちはいつも静かに見ていた。地下鉄に響き渡るジャックの咆哮は、サテライトにいた頃よりも一層、自信と気品に満ち溢れているようにも見えた。
彼がサテライトを去り、シティのキングとして君臨してから二年の月日が経っていた。たちがジャンクの山から必死に新しいDホイールのパーツを探し当てていくその最中で、ジャックはシティのキングとしての道を着実に歩んでいた。不敗神話、キング・オブ・キング。彼の名がネオドミノシティ中に轟くまで、そう時間はかからなかった。
「出るんじゃない。行くだけだ」
新しいDホイール製作の目的を、シティへ行くためと定めた遊星は、仲間たちにここから去るのかと小言を言われるたびにこの言葉を口にした。そして、シティのネオンを遠巻きに見つめる彼の瞳に抱かれた野望の色は、ジャックとは又違った熱を次第に帯びるようになっていた。
は、泥や埃で汚れながら見つけたパーツを遊星に手渡すたび、彼もジャックのようにここから去ってしまうのではないかという不安に駆られたが、彼のこの言葉はいつも彼女の一抹の不安を根底から取り払っていた。ただ行くだけ。去るわけじゃない。遊星は必ず帰って来る。はそう自分に言い聞かせる。
「遊星、ジャックに会えたらどうするの?」
遊星にスパナを手渡しながらは問うた。一瞬、なめらかな手際がぴたりと止まったものの、彼は即座に答える。遊星の決意は揺るぎないものなのだ。
「Dホイールとスターダストを返してもらう」
そう、とだけは返事をした。遊星はの心情を見透かしたのか、口元を少し歪めて、大丈夫だと穏やかな口調で言った。
「心配するな。取り戻したら、すぐ戻る」
そう言われても、サテライト住民によるシティへの不法侵入など、セキュリティにでも見つかってしまえばあっという間に収容所送りな案件だ。重罪人扱いで、そう簡単に出ては来れるまい。の中に芽生える不安は、ただ単に戻ってこないのではないか、というものだけでなく、遊星が犯罪者としてのレッテルを貼られてしまうのではないかというのもあった。遊星の端正なかんばせに刻印されるマーカーなど、できれば見たくはない。
「は、あいつに会えるとしたらどうしたい」
「私…?」
唐突な問い掛けには小首を傾げた。
もし、再びジャックと会うことができたなら、私はどうしたいのだろう。
ジャックの姿を思い返すたびに胸が痛み、呼吸が苦しくなるのはきっと、彼に対する罪悪感が二年の歳月を経てもほんの少しも拭えないからだ。この生活を永続させることばかりを重きに置き、彼の意思を尊重せず、抱く野望に理解を示さなかった。心を繋ぎ止めることすら敵わなかったのは、現実から目を逸らしまくったツケなのだろう。
「あのね…引っかかってることがあるの。ジャックが去ったあの日から、ずっと…」
「…あの時、ジャックに何か言われたのか」
「俺を苦しめないでくれ。黙って愛させてくれないのなら、俺の前から消えてくれって」
心の内に秘めていたわだかまりのを紐解いていくように、は言葉を続ける。
「私、分かってたの。ジャックは私のことが好きなんだってこと。でもずっと気づかないふりをして、誤魔化してた。ちゃんと向き合わなかった。ジャックの真剣な気持ちを無下にして、私は遊星に逃げてた。ずるくて卑怯で、臆病で、…最低な女」
「…………」
「どうしたいか…かあ。もちろん遊星やラリーにしたことは許せないし、それとこれとはまた違う問題なんだけどさ…ジャックを追い詰めた一因はきっと私にもあるから…だから、できることなら、ジャックに謝りたい。ちゃんと、ごめんねって、伝えたい」
昔のようにみんなで笑って楽しく過ごせたら、なんて高望みはしない。ただ誠心誠意、彼の大切な気持ちを無下に扱ったことをひたすら謝りたいだけだった。この言葉に嘘偽りはない。
二年間抱え込み続けた心情を一気に吐露したら、すっと肩の荷が降りたように体が軽くなったような気がした。「許してもらえるか分からないけどね」と言って遊星に苦笑を向ければ、彼は真剣な面持ちで「そんなことはない」と、小首を横に振って見せる。
「絆があれば、失ったものもいつかは取り戻せるさ」
なんて説得力のある言葉なんだろうとは思った。遊星は不可能を可能にする不思議な力を持つ男だ。そんな彼が言うのであれば、きっとそうなのだろう。ふと目頭が熱くなった。
「二人がまた顔を合わせられるよう、なんとかする。それまで待っていてくれ」
もう一度、ジャックに会いたかった。会って、謝って、許されるのならまた、彼の名を呼びたい。
それだけで、この地獄の季節から抜け出せる気がするのだ。
完全なる完成まであともう一歩のところで頓挫しかけていたが、ラリーが”持ってきた”パーツにより遊星のDホイールは著しい進化を遂げた。勿論、代償はあった。ラリーの持ってきたパーツが案の定盗品だったので、セキュリティに追いかけられる羽目になったのだ。しかし、遊星がセキュリティの追跡を引きつけ、取引と称したライディングデュエルを行い、見事勝利したおかげで事なきを得る結果にはなったが。
時は来た。決行は深夜11時15分。夜空に浮かぶ満月が、一つの物語の開始を告げている。
「遊星」
ラリーが声を掛けると、遊星は視線を仲間たちに移した。
「成功を祈ってるぞ」
「お前ならやれるさ。もう、ここまで来たらもう何も言わない。行って来い!」
「そしてジャックに会ったら…、んーまあ、いいや。早く戻ってこいよな」
ナーヴ、ブリッツ、タカがそれぞれ激励の言葉を述べる。期待に応えるように、遊星は静かに頷いた。
「あ、待って!」
ラリーは何かを思いついたのか、遊星の元へ駆け寄った。そうして、一枚のカードを彼に手渡す。
「これ、お守り!」
「これは…」
「ワンショット・ブースター!」
「お前のお気に入りだろう」
「うん…でもいいんだ。そいつであのパイプラインを突破できますように」
祈るように、あるいは願いのように、ラリーは指を組んだ。遊星はそのカードをデッキに収める。ハンドルを捻り、ヘルメットを被ると「必ず返す」と言い、真剣な眼差しをラリーに送った。
「遊星…」
皆が言葉や行動で遊星の背中を押す最中、だけは不安な面持ちを隠すことが出来ずにいた。そんな彼女の姿を見て、ナーヴが背中をぱん、と叩く。顎をくいっと動かし、そんな顔してないでちゃんと見送りの言葉一つくらい言ってやれよ、と訴えかけているようだった。そうだ。私一人だけこんな暗いままじゃ、遊星の決意を無下にするようなものだ。は胸に手を当て、息を吸って、吐いて、深呼吸をしてから遊星の元へ駆け寄る。
「どうか無事で…気をつけてね。どのくらいあっちに居るのか分からないけど、ちゃんとご飯食べて、ちゃんと睡眠もとって、それから…」
「おいおい、マーサかお前は」
後ろでブリッツが笑いながらツッコミを入れた。つられて遊星も、ほんの僅かにではあるが、顔を綻ばせた。
「大丈夫だ。長居はしない。すぐ戻る」
「そうだよね、スターダストとDホイールを取り返したら、戻ってくるんだもんね」
「ああ…だけど、奪われたのはそれだけじゃないからな…」
遊星は至って真剣な面持ちでを見つめながらそう言った。それだけじゃない?はて、何のことやら、と仲間たちはそれぞれ顔を見合わせた。ラリーは不思議そうに、見つめ合う遊星とを交互に見遣る。当のも、「他になにかあったっけ?」とでも言わんばかりの表情を浮かべていた。
彼はそれ以上何も語らなかった。征く道を見据えて、Dホイールを走らせる。
「遊星ー!がんばれー!」
瞬時に小さくなる遊星の背中に向けて、ラリーは叫んだ。
遊星の動向を見守るべく、彼女らは双眼鏡とパソコンを片手に外へ走り出した。ビルの階段を駆け上がりながら、先ほどの遊星の言葉に引っかかりを覚えていたのか、タカが問う。
「なあ、もなにか盗まれてたのか?」
「えっ?いや、私はなにも…」
「だよなぁ?」
うん、と彼女は小首を縦に振った。遊星の言葉に、全くもって心当たりがなかったのだ。ジャックとの最後のやり取りを端的に話はしたものの、だからと言って何かを盗まれたわけでも、奪われたわけでもない。遊星のあの一言が一体何を指しているのかは、誰にも分からなかった。
「おい、お前ら!口より足を動かせっての!」
階段を先導するナーヴが遅れをとる二人に声をかける。時刻は既に11時56分。パイプラインの流出が止まるまであと少し。
遊星がパイプラインを無事突破してから、それはもう形容しがたいほど不安で不安で仕方のない日々が続いた。すぐ戻ってくると言っていたとしても、それが一日二日でないことは明白だったし、もしかしたら一ヶ月、もしくはそれ以上かかってしまうかもしれない。そんなに心配するなよ、あの遊星だぞ?と励まされても、なぜか胸騒ぎだけは治まらなかった。
そしてその胸騒ぎは杞憂に終わることはなく。
遊星の住処で皆と談笑をしていた最中に、スーツを身に纏い、武装した覆面の男たちが乗り込んできて、彼女らを攫って薄暗いコンテナの中に閉じ込めたのだ。
そこから抜け出せたのはどれほど時間が経過した後なのかは分からなかった。突然かちゃり、とロックが外れる音がして、仲間たちはなだれ込むように外に出ることができた。日差しが眩しい。日を手で遮るようにして外に出ると、ジャンクに紛れて一台のモニターがスタジアムの映像を映し出していた。モニターから漏れる声に導かれるように、彼女たちはそれに群がる。
「お、おい!遊星に!」
「マーカーが?!」
大きく映し出された不動遊星の頬には、犯罪者の刻印が為されていた。
ああ、ほら、やっぱり。胸騒ぎの真の正体はこれだったのだ。
赤き龍が舞い、眩い光と共に映像が乱れ、再度映像が映し出された時には既に勝負の決着はついていた。ジャックと遊星、二人の因縁の対決は遊星の勝利にて終着。それは同時に、遊星がシティのニューキングとして君臨することを意味していた。
「なあ、知ってるか?この間のフォーチュンカップでサテライト出身者がキングを打ち破ったらしいぜ」
勿論、その話題は瞬く間にサテライト中にも轟くことになった。サテライト住人、皆が遊星の話題を口にしていた。褒め称えるものもいれば、イカサマだろ、ただの出来レースだ、と非難するものもいた。
色々言ってくれちゃって、ジャックのことも、遊星のことも何も知らないくせに。市場の雑踏を歩みながら入り込んでくる人々の話題には耳を傾けていた。
遊星は勝ったのだ。そして、スターダストを手にした。つまりそれはサテライトへの帰還を意味している。どのような手段を用いてこちらに戻ってくるのかは分からないが、兎に角、彼は帰ってくるのだ。
でも、ジャックはどうなんだろう。キングの座を奪われた今、シティに残り続けることを選ぶのだろうか。
残り続けられたらきっと、二度と彼には会えない気がする。
遊星はいつしか「なんとかする」と約束をしてはくれたものの、いざそれをどうやって実現するかが問題なのだ。ジャックはこのサテライトを忌々しいごみ溜めと形容しているくらい、憎くて仕方ない故郷なのに、再度足を踏み入れてくれることがあるのだろうか。
そんなことをぼうっと考えていた時だった。脇道に居た、眼深くカーボーイハットを被った不審な男に、突然腕を掴まれ、人気のない小道に連れて行かれたのだ。
「あんたがだな?」
「ちょっ、や、誰?!」
強盗か強姦魔か何かの類かと思い、身体を強張らせた。大声を出し助けを求めようにも、唐突な恐怖に苛まれ言葉が思うように出てこない。ささやかな抵抗として、ありったけの力を込めて掴まれた腕を振り払う動作しかできなかった。
「待て待て待て、落ち着けよ。怪しいもんじゃない。俺は遊星の使いだ」
「遊星の?」
不審な男は帽子を脱ぐと、しっ、と嗜めるように口唇に人差し指を当てた。キョロキョロと辺りを見渡し「あんまり人に聞かれるとマズイ話なんでね」と小声で告げる。
「俺は雑賀ってもんだ。時間がないから端的に言うぞ。これからシティに行け」
「シティに?私が?どうやって」
「今、港に連絡船が停泊してる。そこに青い帽子とつなぎを着た協力者がいる。そいつの所に行け。後はそいつが案内してくれる」
「ちょ、ちょっと待ってください、どういうこと?」
「時間がないと言ったろ」
「でも、どうして」
「ジャックに会って謝りたいんじゃないのか?」
その言葉に、は眼を見開いた。なぜそのことを知っているのだ?遊星の名を借りた不審者かと頭の片隅では思っていたが、どうやらこの雑賀と名乗る男、本当に遊星の知り合いのようだ。
「詳しいことは俺も知らないがね。遊星の頼みなんだ。とにかく、ほら、早く」
雑賀は彼女の背をぐいぐいと押して、走るように促した。突然現れた謎の男、シティ、遊星、ジャック、連絡船、青い帽子のつなぎの男。頭が混乱している。
「走れ!」と雑賀が叫んだ。その声に押されて、は考えることを止め、走り出した。
そうだ。走るしかない。呼吸が乱れて、髪がぐちゃぐちゃになって、足がもつれたって構わない。今のにできることは港へ向かってがむしゃらに走ること。戸惑いも動揺も疑いも要らない。ジャックに会えるチャンスが確かに、目の前に、この手の内にある。もう迷わない。もう躊躇わない。もう逃さない。もう誤魔化さない。
私はジャックに会いたい。
だから、どんな時も、いつだって前に進むしかないのだ。
夢を見た。サテライトを去ってから幾度となく見た夢。世界で一番愛おしい女を泣かせる夢。しかし、これは夢などではない。ジャック自身の記憶だ。サテライト、シティ、ネオン、荒れ狂う海、裏切りの故郷、友との決別、それからとの別れ。忌々しくて、思い出したくもない、愛を捨てた男の地獄。
頰を撫でる冷たい風がジャックをまどろみから覚醒へと導いた。虚ろな瞳に映るは真っ白な天井、鼻に付くは薬品の匂い、身体を包むは柔らかな寝具。病院にいるのだな、とぼんやりとした意識の中で思った。赤き龍に導かれ、超次元とも云える場所で因縁の死闘を繰り広げ、結果、遊星に負けた。転倒した際に打ち付けた頭と腕に痛みを覚える。
それと同時に、手に、あたたかな感触。
「…なのか?」
確認するより先に、口走っていた。重い頭を傾けて、開ききらない瞳にその姿を収める。そこに居たのも、あたたかな感触の主も、紛れもなく確かにだった。額に汗を滲ませて、呼吸をわずかに乱れさせている。
「…どうしてここに」
「そんなの、会いたかったからよ…」
「夢じゃ…ないんだな…」
雑賀という男がここまで来るよう導いたのだと、事の顛末を彼女は端的に話した。そして話しながら、瞳から大粒の涙を流し始めた。ジャックは、重ね合わせられた頼りなげほどか細い手をやんわりと握る。
「なぜ泣いている…」
「どうしてだろう、分かんないや」
嗚咽と共に、彼女はそう言った。拭っても拭っても溢れる涙と病室に響き渡る嗚咽を前に、ジャックは心が痛む思いだった。
「オレは…お前を悲しませてばかりだ」
忘れる事のできない過去の記憶の中でも、夢の中でも、そして今も。どうしてオレは、お前を泣かせる事しかできないのだろう。ジャックは力の入らない腕をどうにか上げて、手のひらを彼女の頬に添えると、大切なものを慈しむかのように親指で雫を掬ってやった。
「そんなことない、そんなことないよ」
添えられた手に、も手を重ねる。そして瞼を閉じて、微笑んだ。
「私、ずっとね、あなたに謝りたかった」
ぐず、と彼女は鼻をすする。
「ごめんなさい。私、あなたをずっと苦しませてた…ごめんね、本当にごめん…」
「……もういい…いいんだ。所詮、過ぎたことだ」
制止を求めても何度も何度も繰り返される謝罪に、ジャックの胸はより一層痛んだ。辛かった。何より情けなかった。こういう時にこそ、何か気の利いた台詞の一つでも言えたらいいのに、このなけなしの意識の最中ではそんなものすら思いつきやしない。
「さん、そろそろ…」
外から焦りを帯びた男の声がした。窓の掃除員に扮した男が、掃除をするふりをしながら室内の様子を伺っている。なるほど、そうやって忍び込んだのか。なんともアナログな手法だなとジャックは鼻で笑った。
「もう、行くのか?」
「うん…」
「そうか…」
「とにかく今はゆっくり休んで、怪我を治して」
「お前にそんな顔をされたままじゃ、治るものも治らない」
「もう、そんなこと言わないでよ」
涙を浮かべたままとはいえ、彼女の屈託のない笑顔を見たのはいつぶりだろう。遠い過去に置き去りにしたはずのの微笑みが、たまらなく愛おしかった。まるで全身をふわりと包み込まれていると錯覚するほどに、優しい微笑みだった。
そうか、オレはずっと、これを待ち続けていたのか。
悲しみに暮れる涙ではない。喜びにあふれ、幸せに満ちた愛おしい女の涙を、ただそれだけを、待ち続けていたのだ。
「名前…」
「ん?」
「名前を…呼んでくれないか」
「…呼んでいいの?」
「ああ…」
「……ジャック」
「…もう一度」
ジャック、ジャック、ジャック…。
何度も繰り返し呼ばれる名前、それは体の痛みを癒すような、心の痛みを和らげるような、胸が膨れるような心地よさを感じる優しい声音だった。
頬に添えていた手のひらから、するり、と力が抜けた。瞼が重かった。二年ぶりの最愛の女の姿をもっとこの目に焼き付けておきたいのに、遠のく意識はそれを許してはくれない。
はジャックの耳元に顔を寄せ、囁く。
「私、待ってるから。サテライトで、あの瓦礫の街で、私はずっと待ってる。身の回りのこと落ち着いたらでいい。だから、また、会えるよね?」
ジャックは静かに、そして緩やかに頷いた。意識が遠のく。の気配も、声も、遠のいていく。
地獄だとばかり思っていたはずの人生が、まるで天国のようだった。身体中に、優しくて柔らかで、手足の端々まで溶けてゆくような幸福感が流れている。きっと、これが幸せというものなのだろう。
かつてない喜びを胸に抱きながら、ジャックは再び深い眠りに落ちた。